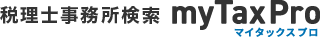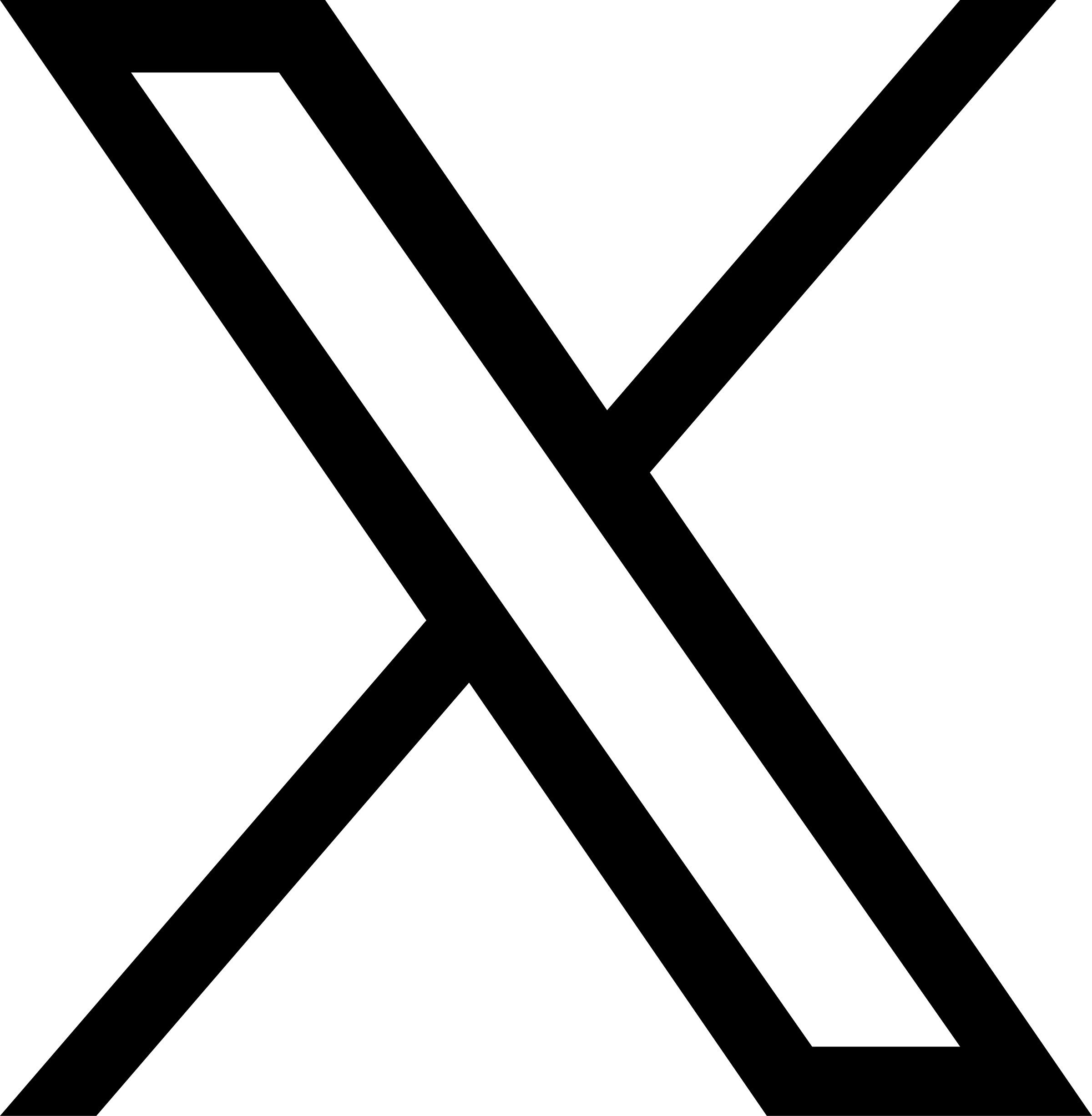💡この記事のポイント
☑配偶者控除を活用すると、実質2,110万円まで贈与税ゼロで住宅を贈与できる
☑高額所得者ほど、収益不動産(アパートなど)を生前贈与する効果は大きくなる
☑賃貸中の建物を贈与する際は、敷金の精算などに注意が必要
☑不動産の生前贈与には、登記費用・登録免許税・不動産取得税・贈与契約書の印紙税などのコストがかかる
☑贈与により取得した宅地等には「小規模宅地等の特例」が適用されないため、贈与するか相続させるかの判断は慎重に行うべき
閉じる開く
- 1.はじめに
- 2.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用した住宅の贈与
- 3.収益を生む不動産を贈与する効果とは
- (1) 将来の地代や家賃を無税で贈与する効果がある
- (2) 将来の所得税・住民税対策になる
- 4.アパートなど賃貸中の建物を贈与する際のポイント
- (1) 満室時点で贈与すると有利
- (2) サブリース契約や企業への一括賃貸契約に
- (3) 賃貸借契約書や振込口座の変更が必要
- (4) 贈与の際には敷金相当額の精算を
- (5) 賃貸建物は修繕してから贈与すべき
- 5.不動産の生前贈与の注意点
- 6.まとめ
1.はじめに
元気なうちに自宅や収益不動産の生前贈与を検討される方は多いのではないでしょうか。不動産は高額であるため、生前贈与によって相続財産を減らすことは相続対策につながります。また、贈与税は贈与した時点での不動産の価値をもとに納付税額が算出されるため、将来値上がりが期待できる不動産については、値上がりする前に贈与することで税負担を抑えられる可能性もあるでしょう。
一方で、贈与ではなく相続により不動産を取得し特例などの制度を活用することで税負担が軽く済む場合もあります。
どのような場合に「不動産の生前贈与」が有効なのかは個々のケースによりますが、「贈与税の配偶者控除を活用した住宅の贈与」や「収益不動産の贈与」を通じて、確実な資産の承継や相続税の負担軽減が可能になることがあります。特に高額所得者の場合、アパートなどの賃貸建物を贈与することで収益が受贈者(贈与を受けた人)に移るため、贈与者(贈与した人)の所得が減り、所得税や住民税の対策にもなるのです。
とはいえ、不動産の贈与は現金ほどシンプルではありません。登記などの手続きに加えて登録免許税や不動産取得税などのコストがかかりますし、収益不動産を贈与するのであれば敷金の精算などにも注意しながら進める必要があります。
そこで、本記事では、「配偶者控除を活用した住宅の贈与」について説明するほか、収益不動産(アパートなどの賃貸建物)を中心に取り上げて生前贈与の効果やポイントを紹介しています。また、不動産の贈与に関する一般的な注意点も解説していますので、ご一読ください。不動産の生前贈与を検討する上で、本記事の内容が役立てば幸いです。
2.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用した住宅の贈与
冒頭で触れたように、長年連れ添ってきた配偶者の老後の生活を保障するために、生前にマイホームを譲っておきたいと考える方もいるでしょう。住宅を贈与すると夫婦間でも原則、贈与税がかかりますが、配偶者控除(おしどり贈与)の特例を活用すれば贈与税の控除を受けることが可能です。
(1) 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは
住宅を贈与すると夫婦間でも贈与税がかかりますが、婚姻期間が20年以上である配偶者から「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための資金」の贈与を受けた場合には、贈与税の課税価格から配偶者控除として2,000万円を控除することができます。また、贈与税の基礎控除110万円も同時に適用することができますので、実質2,110万円まで贈与税ゼロで贈与できます。これを贈与税の配偶者控除といいます。
(2) 贈与税の配偶者控除の適用を受けるには?
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには次の要件を満たす必要があります。
①婚姻期間が20年以上であること
②贈与した財産が、配偶者が住むための住宅(国内にある居住用不動産)であること
または、配偶者が住むための住宅を取得するための金銭であること
③贈与した年の翌年3月15日までに、その住宅に配偶者が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること
ただし、この特例は同じ配偶者からは一生に1回しか受けることができないため、贈与のタイミングを慎重に検討する必要があります。婚姻期間は戸籍に入籍された期間で計算しますので注意しましょう。また、この規定の適用により居住用不動産の贈与について贈与税が課税されない場合でも、不動産取得税と登録免許税は納税する必要があります。
なお、夫婦間の居住用不動産の贈与については、「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」があったものと推定され、遺産分割の時には除かれることとなります。つまり、贈与された居住用不動産は相続時には「すでに配偶者のもの」として扱われ、他の相続人との遺産分割の対象から外れるため、相続トラブルの防止にもつながります。
3.収益を生む不動産を贈与する効果とは
資産家にとって、賃貸アパートなどの収益不動産を贈与することは有効な相続対策になります。事業用借地権によって賃貸している土地や駐車場用地として貸している土地、ロードサイド店舗として貸している家屋など、定期的に地代や家賃を生む収益物件である不動産を贈与すると、次のような効果が期待できます。
(1) 将来の地代や家賃を無税で贈与する効果がある
例えば、家賃収入から諸費用を差し引き、これに係る所得税・住民税を差し引いた手取りが年間500万円あったとします。生活費を年金収入で十分賄えている場合、その分将来の相続財産が増えていくことになります。
賃貸住宅や店舗などの収益不動産を贈与すると、贈与時に贈与税は課税されますが、その後の収益は受贈者のものとなるため、結果的に収益を無税で贈与し続ける効果があります。贈与した側は「500万円×経過年数分」の相続財産の増加を防ぐことができますし、受贈者にとっても将来の相続税の納税資金を貯めることができます。
(2) 将来の所得税・住民税対策になる
「はじめに」でも言及したように、収益不動産を贈与すると、その後の収入が受贈者に移ります。贈与者にとっては、その分所得が減りますので、毎年かかっている所得税・住民税が少なくなります。所得税は超過累進税ですので、高額所得者ほどその効果は大きくなるといえるでしょう。
4.アパートなど賃貸中の建物を贈与する際のポイント
(1) 満室時点で贈与すると有利
賃貸中の建物を贈与すると、建物の固定資産税評価額から借家権割合として30%控除して評価することとされています。しかし、贈与時点で空室があると、その空室については控除がありませんので、満室時点で贈与するのが有利です。

(2) サブリース契約や企業への一括賃貸契約に
賃貸中の建物を贈与した側がその敷地を所有していてその後亡くなった場合、相続財産としてその敷地を評価するときに贈与時点の入居者が入居し続けていれば「貸家建付地」として評価することになります(「貸家建付地」は「自用地」よりも土地の評価額が低くなります)。
しかし、入居者が入れ替わった場合には、これに対応する土地の評価は「自用地」としての評価となり、「貸家建付地」としては評価されません。これに対応するためには、贈与前にサブリース契約や企業への一括賃貸契約をしておくとよいでしょう。
(3) 賃貸借契約書や振込口座の変更が必要
贈与にあたっては、贈与者と受贈者との間で建物贈与契約を締結し、建物の贈与登記をしなければなりません。贈与後は建物の所有者が受贈者に代わりますので、入居者との建物賃貸借契約書も変更する必要があります。もちろん従来の所有者との契約内容をそのまま引き継ぐ旨の確認書で構いません。
そのほか、賃料の振込口座も新所有者(受贈者)の口座に変更する必要があります。
(4) 贈与の際には敷金相当額の精算を
賃貸建物を贈与する際に敷金の引き受け(精算)がない場合は、敷金の負担を条件に建物を贈与したことになるため負担付贈与として取り扱われます。
負担付贈与とは「受贈者に一定の債務を負担させることを条件に行われる財産の贈与のこと」です。負担付贈与では、贈与財産の価額から負担額を控除した価額に贈与税が課税されます。この場合の贈与財産の価額は「通常の取引価額」となり、建物についても相続税評価額ではなく「時価」で評価されるため受贈者が負担する贈与税額も増加します。また、受贈者が負担した債務相当額で贈与財産を譲渡したことになるため、譲渡益が生じると贈与者にも譲渡所得税が課税されます。
建物の贈与と合わせて敷金相当額を精算している場合は、実質的な負担はないと認定できるため負担付贈与に該当しません。したがって、「建物+敷金相当額の現金」を贈与することで対策できます。なお、この場合は譲渡対価もないため、贈与者に対しても譲渡所得税課税が発生しません。
(5) 賃貸建物は修繕してから贈与すべき
詳細は「5.不動産の生前贈与の注意点」で後述しますが、建物の借入金残高がある場合には贈与が困難になります。そのため、借入金のない賃貸建物を贈与しようとすると、築年数が古いアパートなどを贈与することになるケースもあります。
しかし、築古の賃貸建物を修繕せずに贈与すると、贈与後すぐに大規模な修繕が必要となり、受贈者が家賃収入以上の出費を負担しなければならない場合もあります。そのような事態を防ぐために、修繕の完了した付加価値の高い物件を贈与することがポイントです。修繕費の支払いによって贈与者の金融資産が減ると、将来の相続税の減少にもつながります。
5.不動産の生前贈与の注意点
不動産(特に収益不動産)の生前贈与は効果的な相続対策になり得ますが、贈与にあたっては注意も必要です。贈与を検討する上で知っておきたい注意点を以下にまとめました。

(1) 建物の借入金がある際には要注意
贈与しようとする建物を借入金で建てていて、その借入金残高があるときには、債権者の同意がなければ贈与そのものが困難になります。借入金付きで贈与するという方法(負担付贈与)もありますが、その場合には建物は時価で評価しなければなりません。借入金との調整が必要になり、贈与対策として有効でなくなることもあります。
一方、贈与した側も建物を引き継がせた借入金の額で譲渡したことになり、譲渡所得税が課税される可能性が出てきます。特に建物を取得したときに買換えの特例の適用を受けている場合などは注意しましょう。前述したように、敷金・保証金がある場合にも同様の取扱いとなりますので一定の措置が必要です。
(2) 必ず贈与登記と贈与税の申告を
「公正証書で不動産の贈与をしておけば登記をしなくても贈与が確定し、登記をしなければ税務署等の第三者にはわからないので贈与税の申告をせず、贈与税を支払わないまま歳月が経てば、時効が成立して贈与税なしで贈与できる」と思われている方がいますが、それは大きな間違いです。
平成11年6月24日最高裁判所不受理決定において、「登記もせず贈与税も払っていないのだから、贈与契約は虚偽であり、贈与の成立は引渡し時である登記の時である」という趣旨の判決(平成10年12月25日の名古屋高等裁判所判決)が確定しています。
贈与をしたら贈与登記と贈与税の申告を必ず行いましょう。
(3) 不動産贈与は相続に比べてコストがかかる
そもそも贈与税は相続税と比べて基礎控除額が低く、税率も高くなっています。
また、不動産の贈与を受けると、不動産登記費用や登録免許税、不動産取得税、贈与契約書の印紙税などが、相続の名義変更時に比べて余分にかかることに注意しましょう。
■不動産を「贈与により取得した場合」と「相続により取得した場合」のコストの比較

登録免許税と不動産取得税は、固定資産税評価額に税率をかけて計算します。贈与の所有権移転登記の登録免許税は2%、相続等の場合には0.4%です。また、贈与の不動産取得税は固定資産税評価額(宅地等は令和9年3月31日まで2分の1)に対して3%の税率とされていますが、相続では不動産取得税はかかりません。
(4) 相続開始前3~7年以内の贈与は相続財産に加算される
これは不動産に限った話ではありませんが、例えば親(被相続人)が亡くなって子(相続人)が財産を相続する場合、子が生前に親から暦年課税※によって贈与を受けていたとすると、そのうち被相続人から暦年課税による贈与を受けた財産は、相続開始前一定期間内であれば相続税の課税価格に加算されます。令和5年以前は3年以内、令和6年以降は段階的に延長され、令和13年以降は7年以内となります 。ただし、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額は、相続税額から控除されます。なお、相続開始前3年超7年以内に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されません。
このように、せっかく贈与しても、その贈与財産の価額が相続税の計算に含まれる可能性があるのです。特に不動産の贈与では評価額が高く、相続税負担が想定より重くなるケースもあるため、贈与の検討は早いうちから行う必要があります。
※贈与税の課税方法には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。制度の違いについては、以下の記事をご参照ください。
《参考》「暦年課税と相続時精算課税、どちらが有利?」(5) 贈与された宅地には「小規模宅地等の特例」が使えない
贈与により取得した宅地等については、相続時に「小規模宅地等の特例」を適用することはできません。「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が家族と住んでいた、あるいは事業に使用していた宅地については、家族の生活や事業を守る観点から、課税価格に算入すべき価額を減額する特例のことです。具体的には、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等のうち、要件を満たすもの(特定居住用宅地等)については、330㎡までの部分について、相続税の課税価格から80%が減額されます(下の表を参照)。
■特定居住用宅地等の適用要件

また、アパートなどの賃貸経営に使用している貸付事業用宅地等についても、以下の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を活用することが可能です。
■貸付事業用宅地等の適用要件

(注1)「準事業」とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。
(注2)相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。以下同じです。)を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません。
なお、アパートなどの収益不動産については、賃貸建物のみを贈与により取得し、土地については親から使用貸借している(無償で借りている)場合も多いでしょう。このように土地を使用貸借していた場合には、被相続人がその土地を「貸付事業用」として利用していたとは認められにくく「小規模宅地等の特例」の適用を受けることは難しいといえます。
「小規模宅地等の特例」は、相続する土地の評価額を最大8割まで(貸付事業用宅地の場合は最大5割まで)減額できる制度ですので、要件を充足できるかどうか十分に確認した上で、相続時にこの特例を活用することも有効な対策といえるでしょう。
こうした知識も踏まえて、不動産を贈与するか相続させるかで迷う場合は、税理士などの専門家に相談の上で最適な方法をご検討ください。
6.まとめ
生前贈与のメリットは、贈与する相手やタイミングを自分でプランニングできる点にあります。賃貸アパートなどの収益不動産を計画的に贈与することで、受贈者に収益を移転できる点は有効な相続対策といえるでしょう。
一方で、不動産の贈与には登録免許税や不動産取得税などのコストがかかるほか、贈与することによって「小規模宅地等の特例」が使えなくなるなどの注意点もあります。
贈与と相続のどちらが最適なのかは、資産の内容や今後の生活設計によっても変わります。税理士等の専門家に相談し、安心できる形で大切な資産を次の世代へと引き継いでいきましょう。
参考文献
・『財産承継ニュースvol.49』(TKC出版)
・『事業承継ニュース特集号 不動産相続のツボ』(TKC出版)
・『事例でわかる 生前贈与の税務と法務』坪多晶子・坪多聡美(日本加除出版)

記事提供
株式会社TKC出版 1万名超の税理士および公認会計士が組織するわが国最大級の職業会計人集団であるTKC全国会と、そこに加盟するTKC会員事務所をシステム開発や導入支援で支える株式会社TKC等によるTKCグループの出版社です。
税理士の4大業務(税務・会計・保証・経営助言)の完遂を支援するため、月刊誌や映像、デジタル・コンテンツ等を制作・提供しています。